|
BRONICA S2
|
|||||
 |
|||||
|
|||||
 |
|||||
|
|||||
 |
|||||
|
|||||
 |
|||||
|
|||||
 |
|||||
|
|||||
 |
|||||
|
|||||
 |
|||||
|
 |
||||||
|
||||||
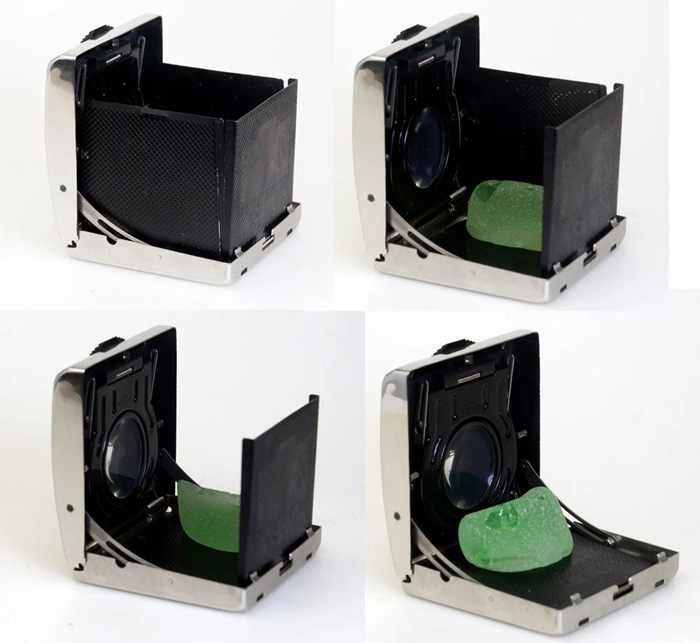 |
||||||
|
||||||
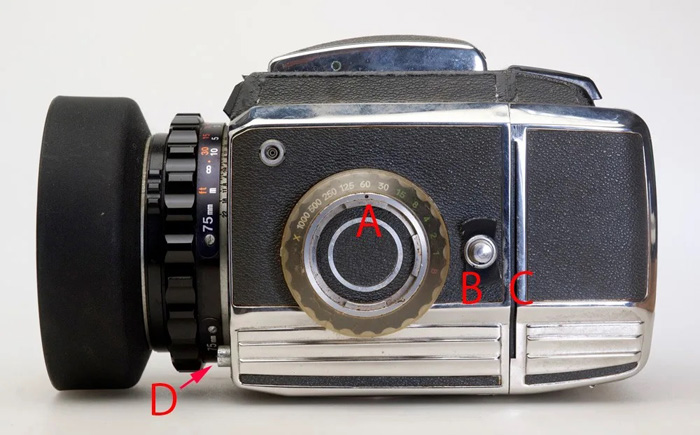 |
||||||
|
||||||
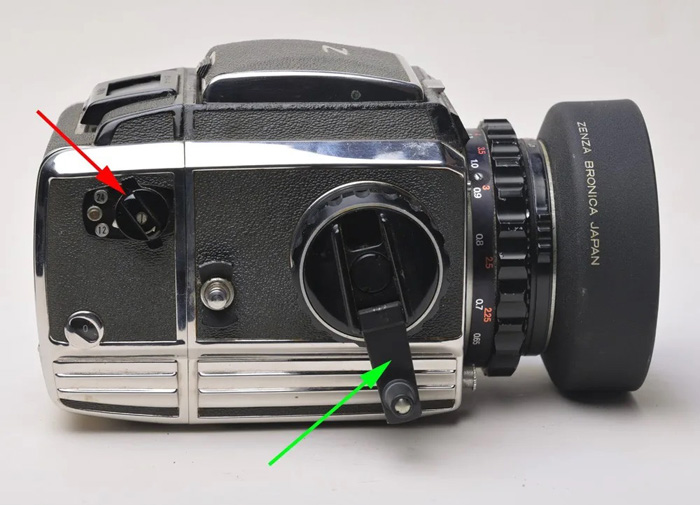 |
||||||
|
||||||
 |
||||||
|
||||||
 |
||||||
|
||||||
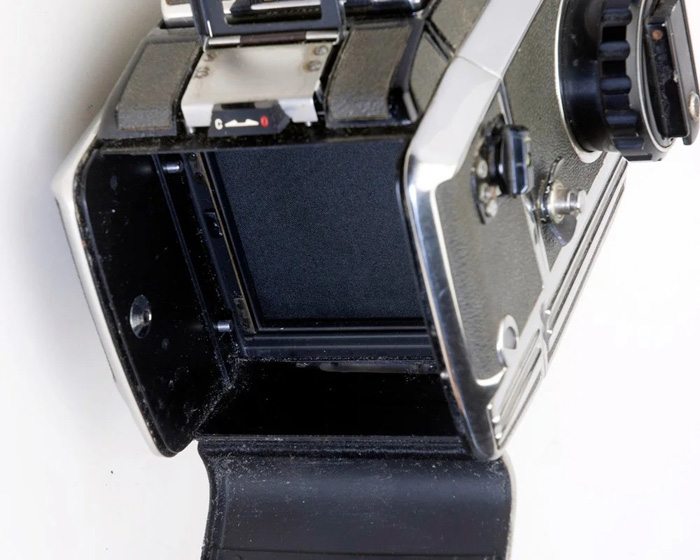 |
||||||
|
 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
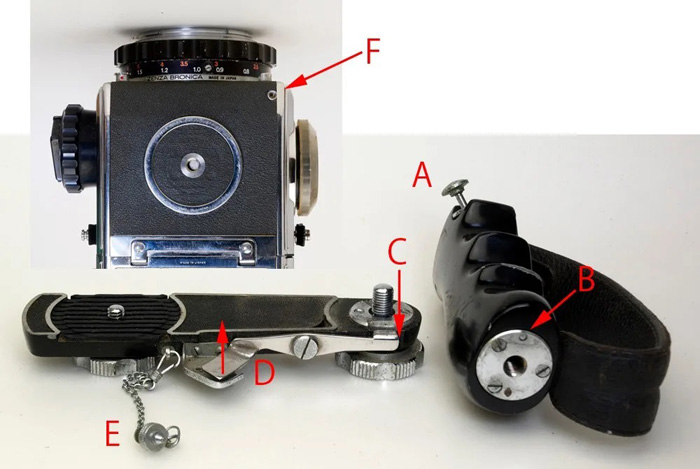 |
||||||||||||||
|
C:BのピンがC部分を下に押す。
|
||||||||||||||
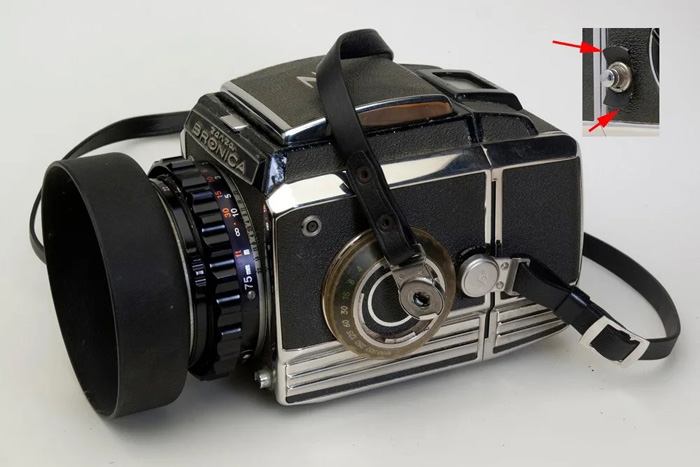 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
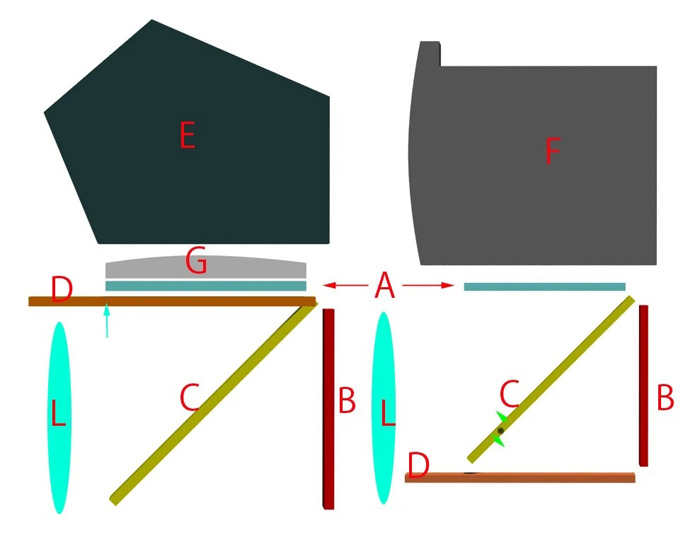 |
||||||||||||||
|
 |
||||||
|
||||||
 |
||||||
|
||||||
 |
||||||
|